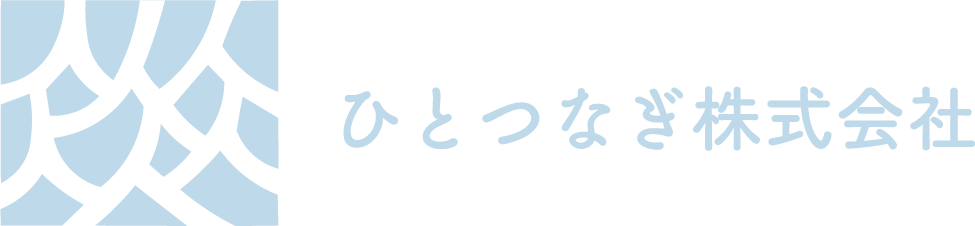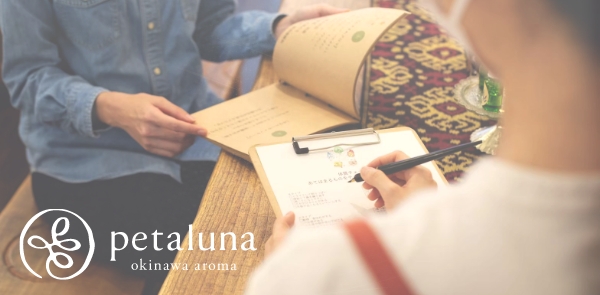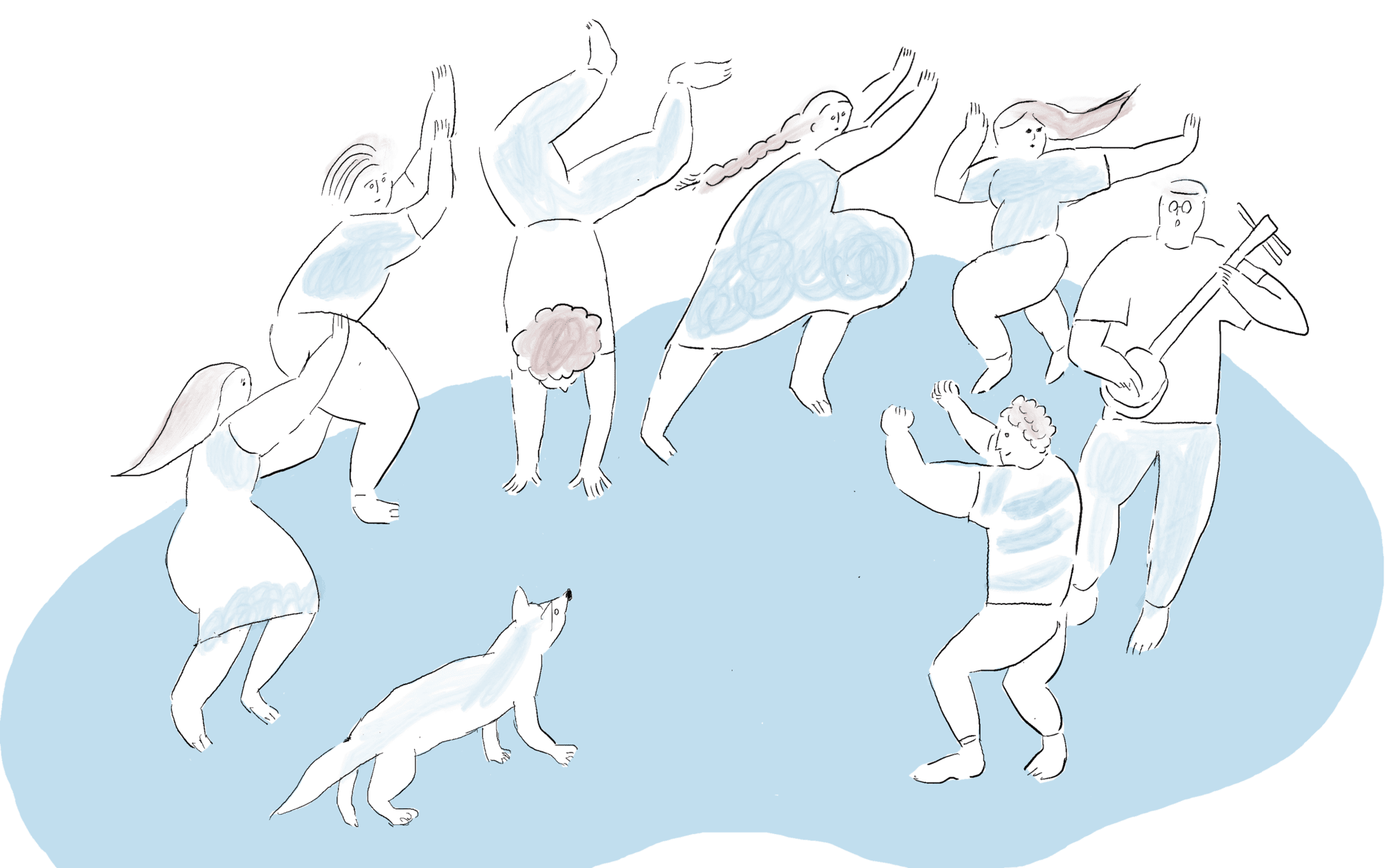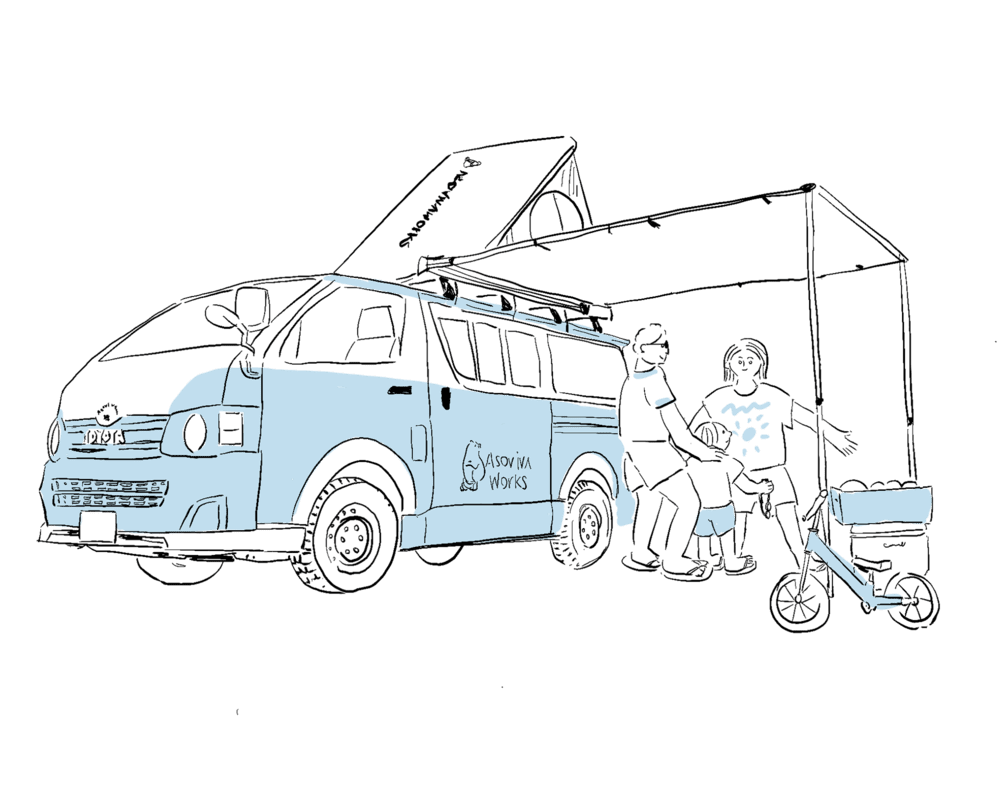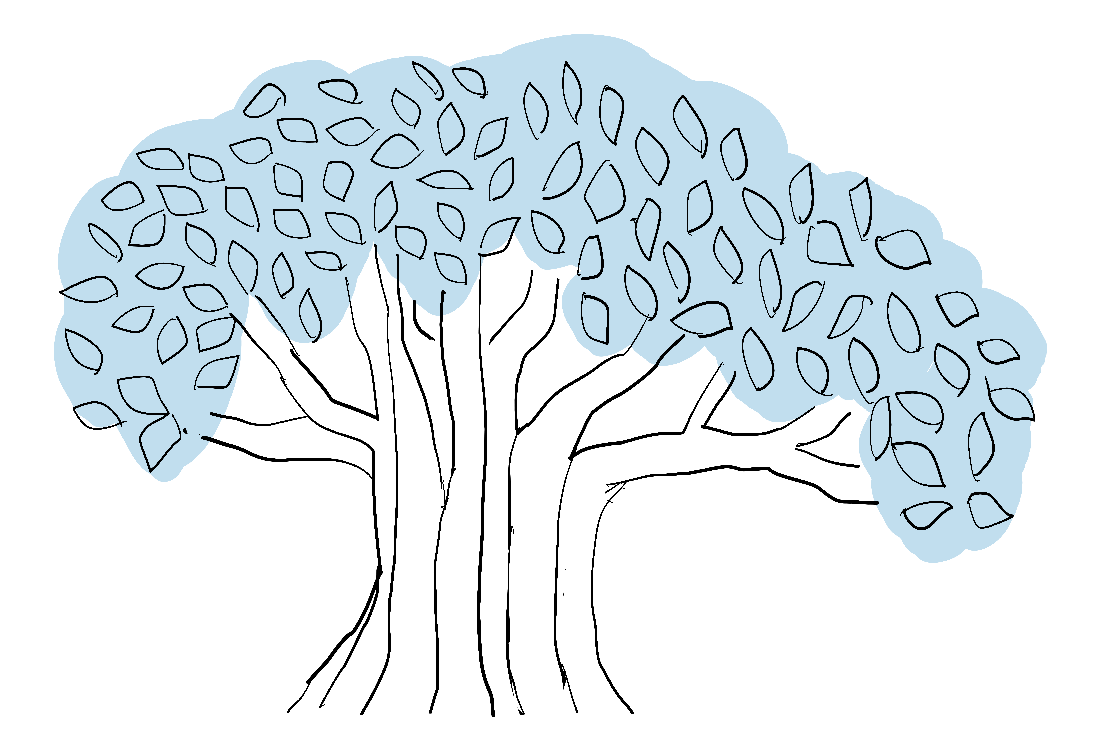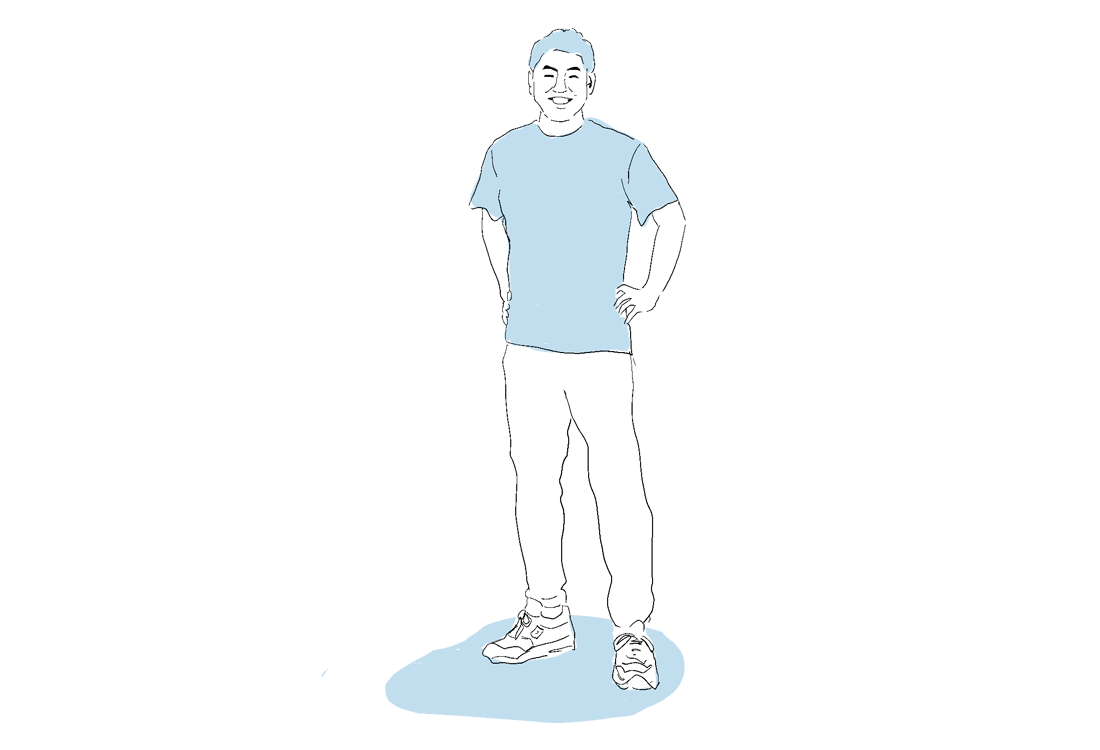こんにちは。ひとつなぎ株式会社の伊藤です。
これまでのブログでは、オーストラリアで学んだ「自然との共生」や「多様な価値観の受容」から始まり、欧米からのお客様との出会いを通して見えてきた新たな可能性、さらには事業承継や理想の組織づくりといったテーマについてお話ししてきました。どのテーマも、「自然と笑顔に溢れた社会を目指して」という私たちの想いを様々な角度から見つめ直す、大切な機会となりました。
今回は、これらの取り組みの先にある「循環型の社会づくり」に焦点を当て、八重瀬町のトリム社様との廃瓶リサイクルの取り組みや、他の企業とのコラボレーション事例を通じて、どのような「つながり」の輪が生まれているかをお伝えしたいと思います。
使い終わったアロマボトルが新しいアロマプレートに生まれ変わる取り組み、沖縄の魅力を広げる循環型の観光モデル、そして移動と宿泊を一体化したキャンピングカー事業と離島との連携など。私たちが歩んできた道のりと、そこから得た学びを皆さんと共有できれば嬉しいです。
捨てればゴミ、活かせば資源 —トリム社との出会いと商品開発
私たちのアロマ部門「ペタルーナ」では、商品容器としてガラス瓶を使用しています。商品の品質を保つために良質な瓶を選んでいるのですが、お客様がアロマオイルを使い切った後、この瓶をどう処分すればよいのかという声を多くいただいていました。
2020年頃、SDGsの取り組みが広がり始めていたタイミングで、八重瀬町にあるトリム社様との出会いがありました。とあるイベントに参加した際、株式会社トリム社の玉那覇部長とお会いする機会を得たのです。社会貢献や持続可能な社会を目指すという想いが共鳴し、すぐに意気投合しました。私たちが抱えていた瓶の回収と処分という課題に対して、トリム社様が快く引き受けてくださったのは、本当にありがたいことでした。
この出会いから、「回収した瓶を再利用して、何か新しい商品ができないか」という発想が生まれ、「地球に優しいアロマプレート」を誕生させることができました。アロマプレート自体はこれまでも取り扱いがあったのですが、地域の企業と連携し、廃材を活用してリサイクルするという視点で生まれ変わりました。実現に向けて両社で協力し、話し合いから商品化までわずか1年もかかりませんでした。
スタッフもトリム社様の工場見学をさせていただき、「捨てればゴミ、活かせば資源」という考え方に触れる機会を得ました。この経験は、私たちにとって大きな学びとなりました。そして、「地球に優しいアロマプレート」は今では人気商品の一つとなり、多くのお客様から評価いただいています。
さらに、使用済みの瓶を持ってきてくださったお客様には「エコポイント」として還元し、現金化できる仕組みも作りました。このように、お客様から私たちへ、私たちからトリム社様へ、そしてトリム社様から新たな商品となってまたお客様へ—という循環型のモデルを構築することができました。
感謝の気持ちから生まれる持続可能な取り組み
この取り組みの根底にあるのは、「感謝の気持ちを忘れない」という想いです。私たちは、ブランドとして持続可能なものづくりに取り組む必要があると考えています。過度な梱包は避け、リサイクル可能なプラスチックや瓶を活用できる商品開発を常に意識しています。
実は、この考え方の原点は私のオーストラリアでの経験にもあります。オーストラリアではゴミの分別に非常に厳しく、日本の比較的緩やかな対応には驚きを感じた記憶があります。自然を大切にする心は、幼少期から培われた価値観なのかもしれません。
現在、社内では定期的なビーチクリーン活動も行っています。海岸のゴミは深刻な社会問題であり、美しい沖縄の自然に対する負荷を少しでも軽減できるよう、できることから取り組んでいます。このような活動が、トリム社様との価値観の共鳴にもつながったのではないかと感じています。
私たちのスキー事業も含め、全ての事業は自然の恵みに支えられています。だからこそ、自然に対する感謝の気持ちを基盤とした活動を続けていきたいと考えています。
沖縄への貢献—癒しの先進県とキャンピングカーの聖地を目指して
これらの取り組みを通じて培った経験や価値観を、私たちは沖縄全体に広げていきたいと考えています。アロマに関しては、沖縄を「癒しの先進県」「アロマの先進県」にしていきたいという想いがあります。アロマに対する正しい知識を広め、その可能性を多くの方に知っていただく活動を続けています。以前から取り組んできた保育園との連携やワークショップなどの活動も継続し、発展させていく予定です。
また、アソビバワークスを軸に、沖縄を「キャンピングカーの聖地」にしていきたいという夢もあります。キャンプの素晴らしさをより多くの人に知っていただくため、キャンピングカー連盟を立ち上げ、横のつながりを作りながらキャンピングカー文化の啓蒙活動も行っています。
現在、沖縄のキャンピングカーは約30台ほどです。北海道の400台と比べるとまだまだ少ないですが、単に台数を増やすだけでなく、質を高め、特別感や付加価値を提供していきたいと考えています。アソビバワークスも現在の4台から7台に増やす予定で、インフラの整備や、ルートの開発、マナーやルールの発信にも力を入れています。
さらに新たな挑戦として、離島とのコラボレーションにも取り組んでいます。伊江島や粟国島など、宿泊施設が不足している離島において、キャンピングカーを活用した観光モデルを提案できないかと考えています。船にキャンピングカーを乗せて離島へ持っていき、宿泊施設としても移動手段としても活用する構想です。実際、与論島からキャンピングカーを持っていきたいという要望もいただいており、この取り組みは離島の観光課題解決とともに、私たちの事業拡大にもつながる可能性を秘めています。
2025年にはジャングリアの開業により、沖縄がさらに注目されることが予想されます。この機会を活かし、沖縄の新たな観光の形を提案していきたいと思います。特に「海外の方々は体験にお金を払う傾向が強い」という特性を活かした、付加価値の高いサービス開発に注力していきます。
自然への感謝と循環の輪を広げる未来へ
私たちがこれまで紹介してきた地域貢献への取り組みは、すべて「自然に対する感謝の気持ち」から生まれたものです。この感謝の心をさらに具体的な行動に変えていくため、私たちは新たな取り組みも始めています。社員が新しい気づきを得られる場を作り続けることも大切にしており、例えば最近では、瀬底島で自然の恵みを活かした料理や体験に参加する機会を設けました。このような経験を通じて、スタッフ一人ひとりが自然の大切さや地域との関わりについて考えるきっかけになればと思っています。
トリム社様との経験を出発点に、私たちは地域企業との連携の可能性を広げていきたいと考えています。「地球に優しいアロマプレート」で実現した循環型モデルを、他の商品開発にも応用していく予定です。
私たちが社名を「ひとつなぎ」に変更した理由の一つは、まさにこの「つながり」を広げていきたいという想いがありました。アロマ事業だけでなく、キャンプ事業も含めて、事業の枠を超えたコラボレーションを模索しています。協業のテーマを「自然」と定め、自社だけでなく様々な企業と協業することで、新しい価値を生み出していきたいと考えています。
幸いなことに、価値観が合う企業とのコラボレーションについては、これまで良い関係を築くことができています。どのようなパートナーシップでも、互いの価値観をしっかりと確認し合いながら、Win-Winの関係を構築していくことが大切だと考えています。
「捨てればゴミ、活かせば資源」という考え方は、今や私たちの事業活動全体を貫く理念となっています。この価値観をもとに、より多くの循環型ビジネスモデルを創出していきたいと思います。
今後も地域の企業や団体との連携を深め、沖縄の自然や文化を大切にしながら、持続可能な取り組みを続けていきたいと思います。そして、その輪が沖縄全体、さらには日本全体へと広がっていくことを願っています。
私たちひとつなぎは、これからも「自然と人をやさしさでつなぎ、お客様の心豊かな暮らしに貢献する」というミッションを胸に、一歩一歩、前に進んでいきます。沖縄という土地のポテンシャルを最大限に活かしながら、地域に根ざした持続可能な取り組みを続けていきたいと思います。