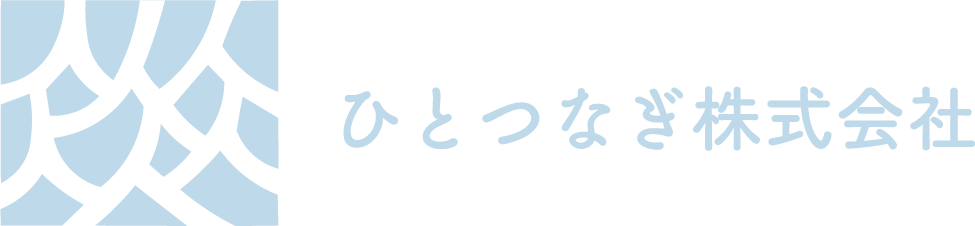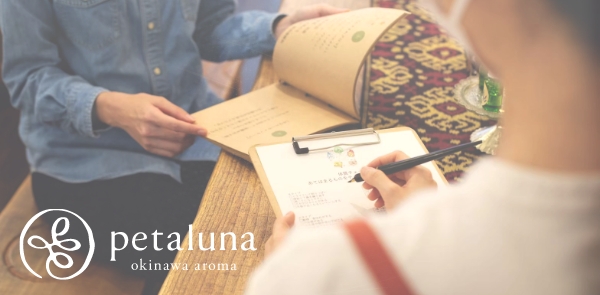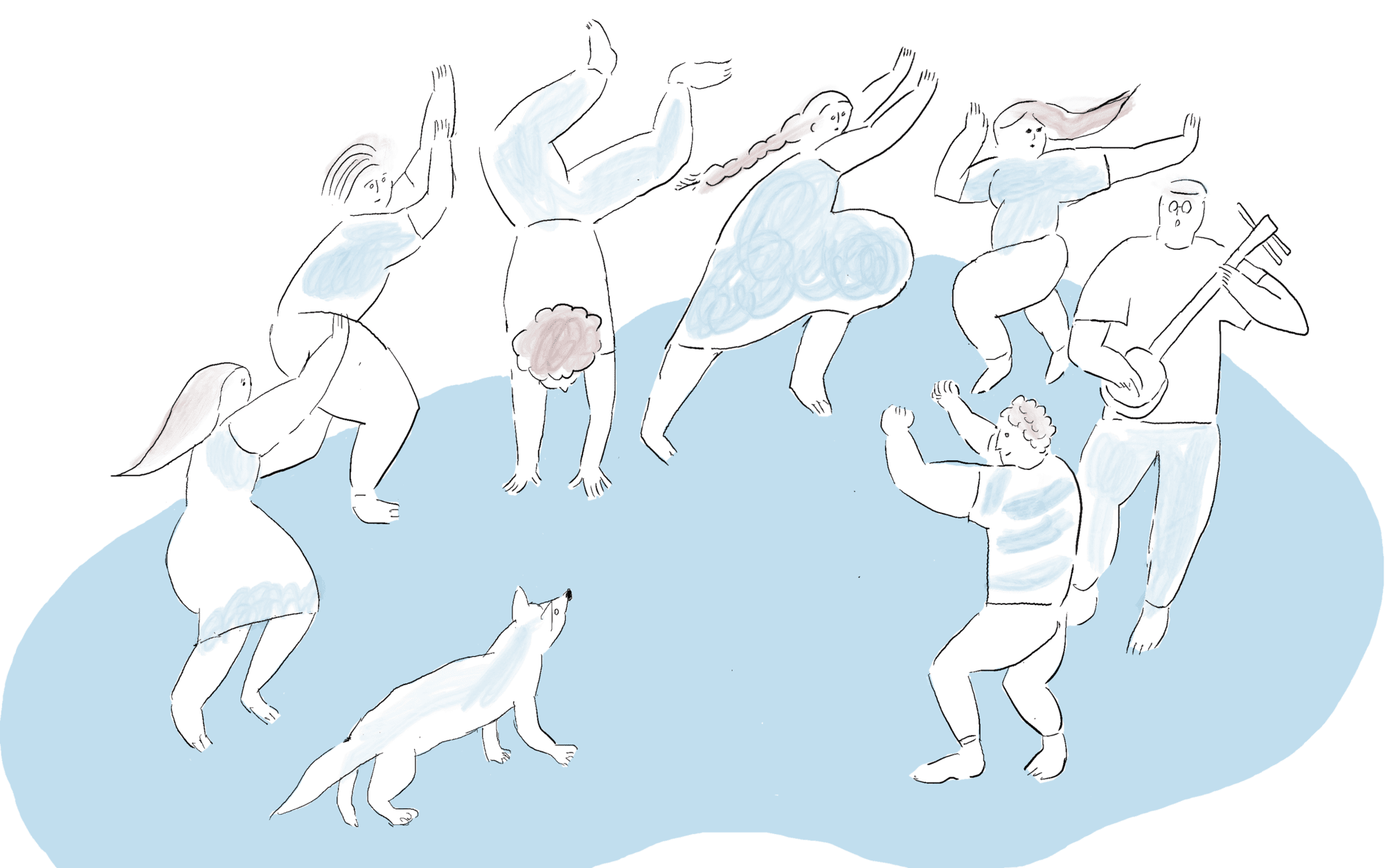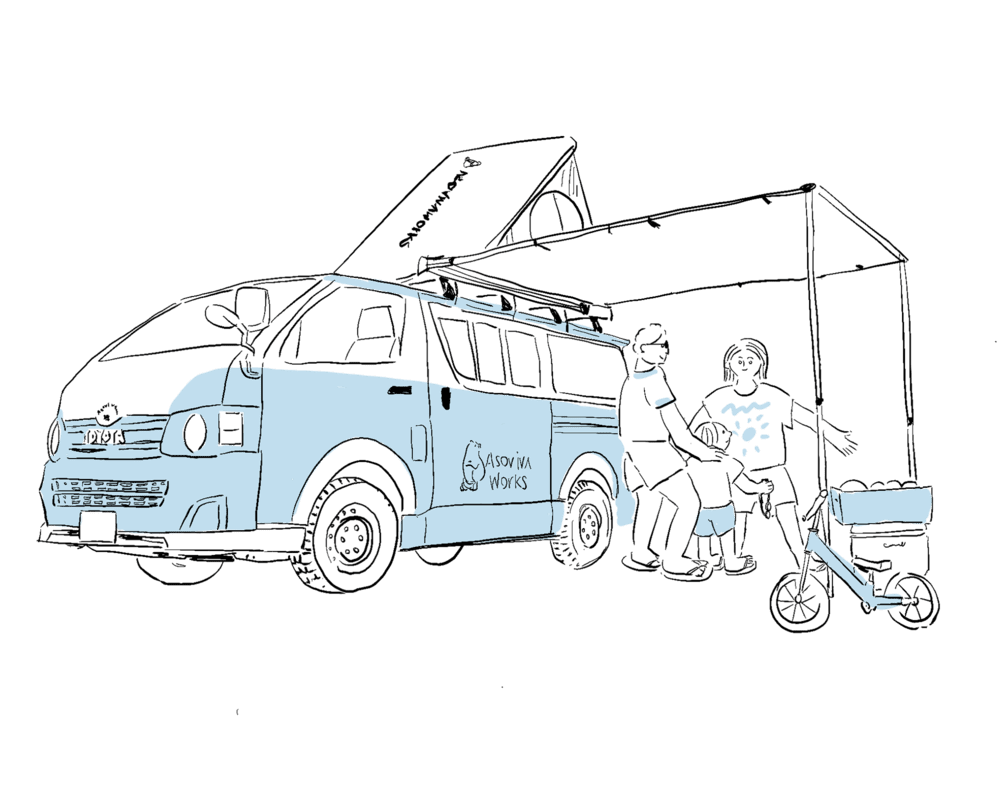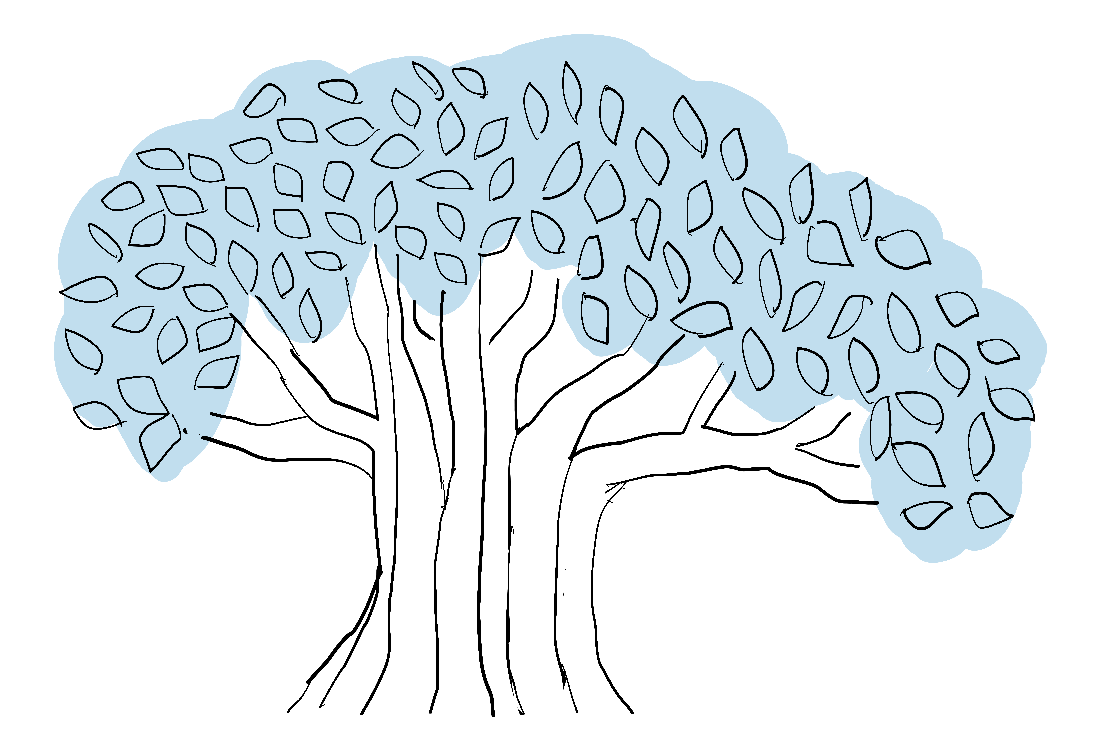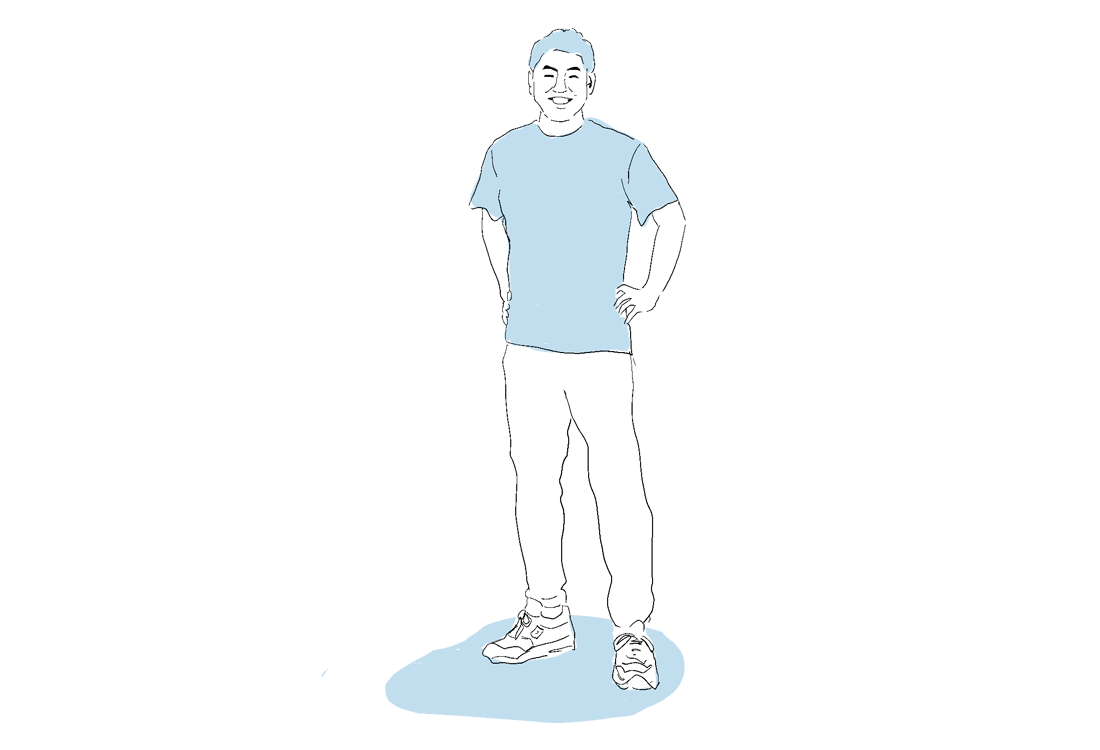こんにちは。ひとつなぎ株式会社の伊藤です。
前回のインタビューでは、欧米からのお客様との出会いから見えてきた可能性と、私たちの取り組みについてお話しさせていただきました。その際にお伝えした「自然と笑顔に溢れた社会を目指して」という想いは、実は私自身の経営者としての歩みの中でも大切にしてきたものです。
今回は、その想いをまた違う角度から、「事業承継」という視点でお話しさせていただきます。というのも、事業承継には不安や葛藤もありましたが、それ以上に新しい出会いと気づきがたくさんありました。父から受け継いだ事業を守りながら発展させていくこと、そして新しい事業との出会いを大切に育んでいくこと。その経験を、率直にお伝えできればと思います。
事業を受け継ぐまでの道のり
私が経営に興味を持ったのは、小学校高学年の頃にさかのぼります。父が広島でスキー事業を起業し、幼い頃から事業を営むことの魅力と課題を間近で見てきたんです。事業を起業することが身近で、やりがいと苦労の両面を見ていました。父からは継承の要請がなかったこともあり、具体的に事業を継ぐことは考えていませんでした。むしろ、姉が起業する姿を見ていく中で、自然と経営への関心が芽生えていったのかもしれません。
大学卒業後は一般企業に就職し、6年間勤務しました。この間、姉がアロマ事業「ペタルーナ」を立ち上げました。この時も漠然と起業への気持ちはあったものの、具体的に事業を継ぐことは考えていませんでした。
その後、結婚と沖縄移住、そして、子供が生まれたことが、大きな転機となったんです。父の会社へ転職し、新入社員として基礎から経験を積み直しました。最初はアロマ部門で県外向けの販売営業を担当し、商品の良さと課題を学びながら売上向上に力を入れていきました。この時期は経営者というより、ひたすら売上を追いかける営業マンでしたね。徐々に組織が大きくなっていく中で、組織の在り方や経営を勉強し始めました。

準備から継承へ、決意の2年間
組織の継承を具体的に考え始めたのは、就任の2、3年前からでした。営業として売上を追いかける中で見えてきた経営課題に向き合うため、より深く経営を学ぶ必要性を感じたんです。営業と財務を担当しながら、セミナーや講習会にも積極的に参加し、組織運営の基礎から実践まで学んでいきました。
本格的な準備を始めてからの2年間は、20名近くいたスタッフの生活を守ることが私の大きな使命でした。期待と不安が半々でしたが、スタッフと共に会社を発展させていきたいという想いを胸に、組織経営の準備を重ねていきました。そして、後継経営者として代表に就任し、スキー用品のレンタル事業とアロマの製造販売事業を引き継ぐことになったんです。
当時、特に意識したのは金融機関との関係づくりです。36歳という若さもあり、見られ方をすごく意識していました。当時の経営状況はあまり芳しくなかったため、どんぶり勘定だった会計システムを見直し、決算時期以外でも数字が把握できる体制を整えていきました。このような準備期間があったからこそ、スタッフや取引先との信頼関係を保ちながら、事業承継を進めることができたのかもしれません。

事業を守り、更なる発展を目指して
事業承継後、これまでに3度の経営危機を経験しました。先代から受け継いだ事業を守り、発展させていく責任を感じる中で、特にコロナ禍での資金繰りには本当に苦労しましたね。借り入れはしやすい環境でしたが、返済への不安は大きかったです。
その後、沖縄でアソビバワークスを立ち上げることになりました。先代から引き継いだスキーのレンタル事業2店舗に加え、新規事業のアソビバワークスをスタートさせるために、経営資源の集中が必要だと考えたんです。そこで、スキー事業の1店舗を売却しようと決断しました。売却に向けた話し合いも進み、契約手前までいきましたが、家族からの反対もあり最終的に頓挫することになりました。今となっては場所的にもとても良い立地だったので、現在は冬季のみの営業とし、将来の広島でのアソビバワークスの展開も視野に入れています。
この時期に気付いたことがあります。それは、経営は決して一人で抱え込むものではないということ。周囲の経営者の方々に相談させてもらっていたのですが、みなさん同じように資金繰りに悩んでいて。お互いに率直に話し合うことで道が開けていったと感じています。
金融機関の方とも、返済期間の相談など、きめ細かなコミュニケーションを心がけました。担当者の方々に恵まれ、いつも親身になって相談に乗っていただいていることに感謝する日々です。

新たな事業承継、研修事業への挑戦
先代から受け継いだアロマやレンタル事業を基盤としながら、新たな展開も模索していきました。その中で、私は企業向けの体験プログラムやワークショップにも強い興味を持つようになりました。沖縄の自然を活かした体験プログラムを考えていた時期に、旅行会社向けに高校生の修学旅行プログラムを提供していた株式会社ノートとの出会いがありました。コロナ禍で売上が立たない状況の中、本業のお菓子製造も成り立たなくなり、研修事業の引き継ぎ先を探していたんです。
研修事業との出会いは、私たちにとって新しい可能性を感じるものでした。そして、ノートの研修事業を引き継ぐこと決意しました。その理由の1つは、イチから事業を立ち上げることの難しさを知っていたこと。2つ目は、ノートの実績を活かせると考えたこと。そして何より、仲間さんの想いに共感できたことです。引継ぎを前提に、4,5件の事業を一緒に実施しながら準備を進めていきました。
引継ぎの準備を重ねながら、2024年1月からは研修事業を完全に継承することになりました。仲間さんには1年間、顧問として相談できる体制を取り、ノートの顧客もそのまま引き継がせていただくことができました。代表者の変更に伴い、社員の皆さんが安心して働けるよう、事前の引継ぎや共有を丁寧に行い、顧客へのサービスにも支障が出ないよう心がけました。
現在、研修事業は県外企業が中心となっています。毎年来られるわけではないため、継続した効果の検証が課題となっていますが、2025年は長期的な研修プログラムの構築と実績作りに取り組みたいと考えています。
沖縄の事業承継の課題と可能性
このように新しい事業との出会いを通じて、地域の可能性を改めて考えるようになりました。実は、広島と沖縄には多くの共通点があるんです。激しい戦争体験があること、豊かな自然と海があること、そしてインバウンド需要が多いこと。コンパクトな地域性と豊かな自然環境は、キャンピングカーやアウトドア事業との相性が抜群です。こうした地域特性を活かした展開を考えていく中で、新たな可能性が見えてきました。
私自身の事業承継の経験から、大切だと感じることがいくつかあります。それは、コミュニケーションと信頼関係の構築、そして財務、人材、権利関係の丁寧な調整です。また、引継ぐ側と渡す側をつなぐ仲介者の存在も重要だと実感しています。この経験は、地域の事業承継について考えるきっかけにもなりました。
沖縄では今後、経営者の高齢化がさらに進んでいく状況にあります。これまで事業を支えてこられた経営者の方々にとって、視野を変えてみることは難しいかもしれません。しかし、自分が当たり前だと思っている事業が、実は他者から見るととても魅力的に映ることがあるんです。その好例として、既存の施設の使い方を変えることで新しい可能性が見えてくることがあります。例えば、工場をスタジオに、学校を宿泊施設にというものですね。このように、既存の事業に新しい価値を見出すことで、思いがけない可能性が広がっていくと考えています。
そのためにも大切なことが2つあります。1つは事業の将来性とメリットを伝えていくこと。そしてもう1つは、事業に対する自分の想いを発信していくことです。現状の収益性だけでなく、その事業が持つ潜在的な可能性を示すことで、新しい道が開けていくのではないでしょうか。私自身も少しずつそこに挑戦し始めたところです。これからも「ひとつなぎ」の想いを大切に、スタッフと共に、一つひとつの可能性を育んでいきたいと思います。